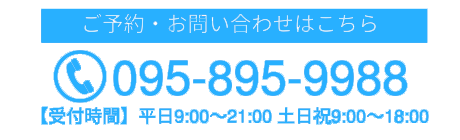財産分与を請求したい・請求された

財産分与を請求したい・請求された
財産分与の請求に関する諸問題
多くの家庭では夫婦の家計は一つとなっているところ、夫婦が離婚する際には夫婦共有財産の清算が問題となります。
とくに夫婦間の収入の差が大きい場合や婚姻期間が長い場合には、財産分与により取得した財産が離婚後の生活費に充てられることが少なくないため財産分与の重要性はより大きくなります。
本ページでは、財産分与の内容、財産分与の対象となる財産、清算割合、請求手続、適切な財産分与を行うためのポイントについて解説いたします。

1 財産分与とは何か?

1.1 財産分与の内容
民法は、離婚に際して夫婦の一方が他方に対し財産分与を請求することを認めています(民法第768条第1項、民法第771条)が、その内容や基準については「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」とのみ定めています(民法第768条第3項)。
そのため、財産分与の内容は条文上明らかとはいえないものの、一般的には清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与を要素としていると考えられています。
このうち財産分与の中心的存在である清算的財産分与については「2 清算的財産分与」の中で詳述します。
1.2 扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚により夫婦間の扶助義務(民法第752条)及び同義務に基づく婚姻費用分担義務がなくなることに照らし認められる場合がある離婚後の扶養を目的とする財産分与を指します。
具体的には、離婚前の夫婦の年齢、健康状態、職業や収入状況、保有している特有財産の状況、清算的財産分与や慰謝料の金額などを考慮して扶養的財産分与の要否が判断されることになります。
もっとも、平成15年に年金分割制度が開始され老後の生活についての生活保障が制度的に担保されたこともあり、近年の裁判例の傾向としては扶養的財産分与を独立して認めるものは多くない印象です。
1.3 慰謝料的財産分与
「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」(民法768条第3項)とされているところ、家庭裁判所は財産分与の中で慰謝料を考慮することが可能です。
もっとも、通常は不貞慰謝料または離婚慰謝料として別途慰謝料を請求する形を取ることが大多数であるため、慰謝料的財産分与が問題になる場面はほとんどありません。
慰謝料を慰謝料的財産分与として請求するメリットとしては、離婚後の財産分与請求に慰謝料を含めることで財産分与の審判手続と慰謝料請求の訴訟手続を2つ行わずに済むという点が考えられますが、本来的には財産分与と慰謝料請求は別個独立した問題であるため審判手続と訴訟手続を別個に進めるというのが合理的ではあります(なお、離婚前に財産分与及び慰謝料を請求するときは離婚調停や離婚裁判の中であわせて請求可能です。)
2 清算的財産分与

2.1 内容
清算的財産分与は、夫婦が婚姻してから別居まで(婚姻前に内縁関係にあった場合には内縁関係が成立したから別居まで)の間に築いたプラスの財産を清算するというものです。
これは、婚姻期間中に形成・維持された財産は夫婦別産制(民法第762条第1項)により名義上は夫婦の一方に帰属するものの、実質的には夫婦の共同財産とみることができることから離婚に際して当該共同財産の清算を認めるものです。
なお、財産分与請求権は協議や審判等により具体的内容が形成されるものである(最二小判昭和55年7月11日民集34巻4号628頁参照)ところ、財産分与の遅延損害金は協議で定めた支払期限の翌日(財産分与の合意をした場合)から、または審判等の確定日(審判や判決により解決した場合)から発生します。
2.2 対象財産
夫婦が婚姻してから別居までの間に築いたプラスの財産が財産分与の対象財産となります。
そのため、婚姻前の財産や相続した財産等のいわゆる特有財産及び基準時である別居後に築いた財産は、「夫婦が築いた」財産とはいえず財産分与の対象とはなりません。
また、債務がある場合、一般的にはプラスの財産から債務を差し引いた残額を財産分与の対象財産としますが、債務がプラスの財産よりも多い場合には債務自体を清算することはありません。
2.3 清算割合(寄与割合)
財産形成に対する夫婦の寄与度は基本的には同等とみるべきであることから、清算割合は原則として2分の1ずつとされています(いわゆる2分の1ルール)。そのため、財産分与を行うと、原則として夫婦は財産分与の対象財産である夫婦共有財産を互いに2分の1ずつ取得するという結果となります。
もっとも、以下のような場合には清算割合が修正されることがあります。
本裁判例は、寄与割合を修正すべき場合の例として以下の例を挙げました。
①夫婦の一方が、スポーツ選手などのように、特殊な技能によって多額の収入を得る時期もあるが、加齢によって一定の時期以降は同一の職業遂行や高額な収入を維持し得なくなり、通常の労働者と比べて厳しい経済生活を余儀なくされるおそれのある職業に就いている場合など、高額の収入に将来の生活費を考慮したベースの賃金を前倒しで支払うことによって一定の生涯賃金を保障するような意味合いが含まれるなどの事情がある場合
②高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成されて、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合
その上で、夫が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し,婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割に修正しました(財産分与の対象財産:約3億1000万円)。
本裁判例は、夫が小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続け当選したという事案について、夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割に修正しました(財産分与の対象財産:約9100万円)。
3 請求手続に関する注意点

3.1 請求方法
協議離婚の場合には協議により財産分与の内容を合意しておく、調停離婚の場合には財産分与について付随的に申し立てておく、裁判離婚の場合には附帯処分の申立て(人事訴訟法第32条第1項)を行っておくことで、離婚と財産分与を一括的に解決することが可能です。
上記解決を取ることが一般的ではありますが、離婚を先行させた上で事後的に財産分与の請求を行うこともあります。
その場合、離婚後に協議により財産分与の合意ができないときは財産分与の調停または審判の申立てを行うことになります(通常、審判申立てを行ったとしても調停に付される(家事事件手続法第274条第1項)ことになるため、調停の申立てを行うことが大多数です。)。
なお、申立てにあたり、分与を求める額および方法を特定する必要はなく、単に抽象的に財産分与の申立てをすれば足りるものと解されています(最二小判昭和41年7月15日民集20巻6号1197頁)。
また、分与の額や方法が具体的に特定されている場合でも、家庭裁判所はそれに拘束されず裁量に基づき判断を行うことが可能です。
3.2 財産分与の審判手続等における注意点
財産分与の請求を行った申立人が相手方よりも多くの財産を有している場合に、相手方から申立人に対し財産分与を命じることができるかについては判断が分かれている状況です。
「財産分与の申立てに対し,裁判所は,清算的財産分与として,当事者双方がその協力によって得た財産の額を考慮事情として認定し,当事者の財産形成の寄与の程度のほか,その他一切の事情を考慮して(一切の事情として,補充的に慰謝料的財産分与や扶養的財産分与を考慮することもある。),分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることになる。この裁判手続は,離婚訴訟の附帯処分として審理される場合においても,非訟事件手続として審理されるものであるから,裁判所は,その判断において,当事者の主張に拘束されることはなく,財産分与の申立てをしていない当事者に対して財産の分与をすることもできる。」
「財産の分与に関する処分の審判(民法768条2項本文,家事事件手続法別表第二の四の項参照)は,財産分与の権利者の義務者に対する財産分与請求権の具体的な内容を形成する手続であり,審理の結果,当該審判の相手方が申立人に対して分与すべき財産の存在が認められない場合は,申立人が相手方に対して分与すべき財産の存在が認められるとしても,申立人に対し,相手方に当該財産の分与を命ずることはできず,当該申立ては却下すべきものと解するのが相当である。」
裁判例の判断は上記のとおり分かれている状況ですが、後記「3.3 期間制限」のとおり財産分与は請求できる期間に制限があること、財産分与調停は審判手続に移行する前には取下げが自由であるところ財産分与を申し立てた当事者により取下げがなされる可能性があることから、財産分与の申立てをされた当事者が他方当事者に対し財産分与を獲得できる可能性がある場合には別途財産分与の申立てを行っておくべきといえます。
なお、審判に対して即時抗告が行われた場合の抗告審では不利益変更禁止原則が適用されない(家事事件手続法第93条第3項が民事訴訟法第304条を準用していない。)ため、即時抗告の申立てを行う場合にはこの点に留意しておく必要があります。
3.3 期間制限
民法第768条
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
上記規定により、離婚から2年が経過すると財産分与の請求を行うことはできません。
期間内に財産分与を請求したというためには、具体的には離婚から2年が経過する前に少なくとも財産分与の調停を申し立てておく必要があります(調停が不成立となった場合には、家事事件手続法第272条第4項により調停申立ての時に家事審判の申立てがあったものとみなされます。)。
なお、財産分与について協議が成立した後の具体的な請求権については5年の消滅時効に(民法第166条第1項第1号)、調停が成立または審判等が確定した後の具体的な請求権については10年の消滅時効にかかります(家事事件手続法第268条第1項、民法第169条第1項)。
4 適切な財産分与を行うために

4.1 特有財産性の主張立証
財産分与を行う際には、婚姻前の財産や相続した財産などの特有財産性を主張立証できるか次第で結論が大きく変わる可能性があります。
事前の対策としては、婚姻前の財産や相続した財産は婚姻後の財産とは別途独立して管理しておく、とくに預貯金については婚姻前の預貯金と婚姻後の預貯金が渾然一体とならないように婚姻前の預貯金を定期預金口座へ入れたり、出入金のない口座に入金したままにしておくといったことが考えられます。
4.2 配偶者名義の財産の把握
財産分与の対象財産は「夫婦が婚姻してから別居までの間に築いたプラスの財産」ではあるものの、上記財産の範囲を確定するためには配偶者名義の財産を把握する必要があります。
仮に配偶者が財産を隠し持っているもののこれを明らかにできなかったという場合、事実上、明らかになっている範囲で財産分与を行わざるを得ない結果、夫婦間で著しく不公平な解決になる可能性があります。
そのため、離婚の話合いになる前の段階から、可能な限り詳細に配偶者の財産状況を把握しておくことが重要です。
4.3 扶養的財産分与の請求を排除しない
「1.2 扶養的財産分与」で述べたように、近年の裁判例の傾向として扶養的財産分与はなかなか認められづらい状況にあります。
もっとも、その他の事情等を考慮し、実際の話合いや和解条件の中では扶養的財産分与的な性質を有する金銭の支払に関する合意をするということが珍しくはありません。
そのため、扶養的財産分与の請求を排除することはなく柔軟に話合い等を進めて行くことが重要といえます。
4.4 未払婚姻費用の清算を検討する
離婚の話合いや別居を開始する際に弁護士へ相談していない場合、本来は婚姻費用を請求できるにもかかわらず請求をしていなかったということがあります。
多くの裁判例は婚姻費用の始期を「権利者が義務者に請求をした時点以降」などとするところ、婚姻費用の審判手続の中で請求時より前の婚姻費用分担金の支払が認められることは基本的にはありません。
もっとも、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」(民法第768条第3項)ところ、請求時より前の過去の婚姻費用が支払われていないという事実を考慮した上で実質的に財産分与の中で清算するということがあります。
そこで、財産分与の中では未払婚姻費用の清算を求めることを検討する必要があります。
※本記事では財産分与を行う場合に押さえておくべきポイントをご紹介いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、財産分与についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。